

楢葉町×東京大学総合研究博物館連携ミュージアム
大地とまちのタイムライン
東大教室@楢葉
「楢葉町×東京大学総合研究博物館連携ミュージアム 大地とまちのタイムライン」のオープンをうけて、楢葉町と東京大学の継続的な共同事業の一つとして「東大教室@楢葉」を開催いたします。東京大学の研究者らによるレクチャーやワークショップ等の教育活動を楢葉町コミュニティセンターで実施してまいります。さまざまな学問分野の研究成果や最新の知見をわかりやすくお伝えします。基本的なテーマを「危機と再生、未来創造」に関わるものとし、とくに「大地とまち」に関わる事象に注目していきます。楢葉町の方々が地域の自然資源や文化資源を再発見し、また研究者が新しい研究を展開させる機会になることを期待しています。
楢葉町の町民や職員の方々をはじめとして、関心をおもちの方々に広く開かれたプログラムです。
参加を希望される方は楢葉町生涯まなび課にお電話でお申し込みください。
主催:楢葉町、東京大学総合研究博物館
共催:大学等の「復興知」を活用した人材育成基盤構築事業
「福島復興知学の深化と展開:ミルフィーユ型人材の育成基盤構築」
企画:東京大学総合研究博物館
場所:福島県双葉郡楢葉町大字北田字鐘突堂5番地の4
楢葉町コミュニティセンター:大会議室
(連携ミュージアム 大地とまちのタイムライン と同一建物内)
交通:JR常磐線「竜田」駅下車徒歩20分、常磐自動車道「ならはスマートIC」より5分
地図:https://goo.gl/maps/AbTiWgvcxyurijwRA
予定:初回は2023年10月21日。毎年度、4月から12月までの偶数月開催の予定。
申込:お電話にて参加をお申し込みください
楢葉町生涯まなび課 0240-25-2492
入場:無料
| 東大教室@楢葉 第12回 終了 日程:2025年12月21日(日) 13:30〜15:00 題目:展示の教室:展示づくりの裏側をお見せします 講師:洪恒夫 (東京大学総合研究博物館 客員教授、展示デザイン) 概要:展示は博物館を構成する一つの機能と言われています。展示とは何か、ということから始め、どうすれば展示がその効果を発揮するのかについてこれまでの経験をもとにお話します。また、ミュージアム「大地とまちのタイムライン」がどのようにプロジェクトとして始まり、どのような狙いをもってつくられていったのかを東京大学総合研究博物館の関連施設の概要と共に詳説します。「展示」をテーマにその本質に迫るひと時を提供します。 チラシ(PDF) |
 |
| 東大教室@楢葉 第11回 日程:2025年10月26日(日) 13:30〜15:00 題目:アマゾンの教室:洞窟と湖が語る人と森の一万年史 講師:金崎由布子 (東京大学総合研究博物館 助教、アンデス考古学) 概要:アマゾンは今、深刻な森林破壊に直面しています。一方で、最近の研究では、古代のアマゾンの人々は、森林をたくみに利用しながら、持続可能な生活を営んでいたことが明らかになってきました。本講演では、アマゾンの洞窟と湖の調査から見えてきた、一万年にわたる人と森の関係史をひもときます。チラシ(PDF) |
 |
| 東大教室@楢葉 第10回 日程:2025年8月24日(日) 13:30〜15:00 題目:昆虫の教室:島嶼でのチョウの保全と地域連携 講師:矢後勝也(東京大学総合研究博物館 講師、昆虫自然史学/保全生物学) 概要:近年では開発や過疎化、温暖化、獣害、外来生物などの影響により、チョウの減少がとても目立つようになりました。中でも、分布の範囲がもともと狭い島に生息する固有のチョウたちが、きわめて深刻な絶滅の危機に陥っています。そこで、小笠原や対馬に暮らす貴重なチョウ類に焦点を当てながら、その現状や減少要因をお話しするとともに、それらのチョウに関する研究や保護活動、地域と連携してめざす持続可能な保全などを紹介します。 チラシ(PDF) |
 |
| 東大教室@楢葉 第9回 日程:2025年6月29日(日) 13:30〜15:00 題目:考古学の教室:農業の始まりを1万年前の西アジアに探る 講師:西秋良宏(東京大学総合研究博物館 館長/教授、先史考古学) 概要:最近のコメ価格高騰にお困りのみなさんも多いことと思います。そもそも食べ物を買わないと生きていけない社会はどうやってできあがったのでしょうか。出発は農業の始まりにあります。この教室では、世界最古の農業が生まれた約1万年前の西アジア社会について考古学の観点からお話しします。その始まりも展開も気候変動がもたらした危機がかかわっていました。チラシ(PDF) |
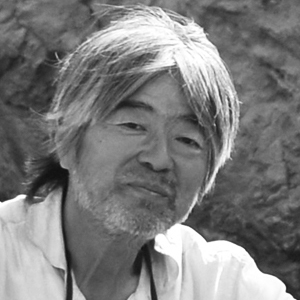 |
| 東大教室@楢葉 第8回 日程:2025年4月20日(日) 13:30〜15:00 題目:健康の教室:ミクロな世界の危機と再生〜危機に陥った体の中で何が起きている? 講師:秋光信佳(東京大学アイソトープ総合センター 教授、分子生物学/放射線創薬学) 概要:熱や放射線など体に害をなす刺激(これを環境ストレッサーと呼びます)に我々は常にさらされています。環境ストレッサーによる健康の危機に陥ったとき、わたしたちの体はどのように対処しているのでしょうか?この謎をミクロレベルで紐解き、人体における「危機と再生」の妙技を紹介します。「生き物ってすごいね!」と一緒に感じましょう!チラシ(PDF) |
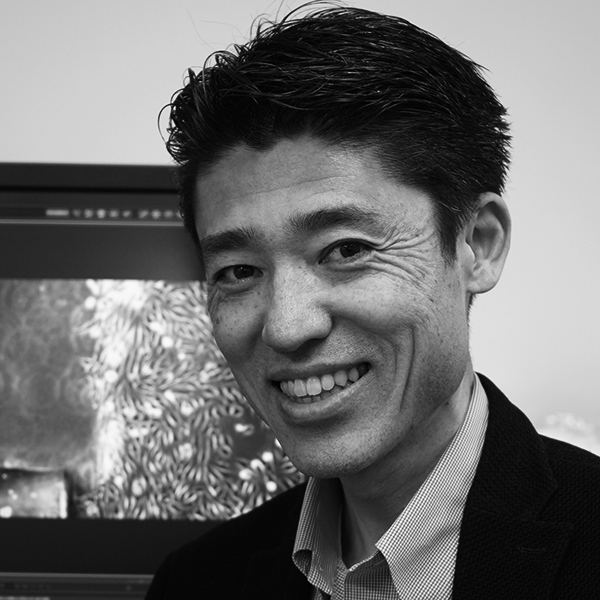 |
| 東大教室@楢葉 第7回 日程:2024年12月22日(日) 13:30〜15:00 題目:地質図の教室:常磐地方の化石と地質図 講師:佐々木猛智(東京大学総合研究博物館 准教授、古生物学) 概要:常磐地方は古くから化石の研究が盛んに行われてきました。その理由は石炭の採掘と関係しています。石炭を探すためには地層の分布を理解することが重要であり、その手がかりとして化石が注目されていました。常磐地方の地質図は3つの異なる版が発行されており、楢葉町に関する興味深い情報も含まれます。古い地質図には炭鉱や炭鉱鉄道の場所も示されています。本講演会では、東京大学総合研究博物館が所蔵する地質図と標本を紹介し、化石からわかる常磐の歴史について解説します。チラシ(PDF) |
 |
| 東大教室@楢葉 第6回 日程:2024年10月27日(日) 13:30〜15:00 題目:古文書の教室:猪狩家文書にみる戦国時代の楢葉 講師:白石愛(東京大学総合研究博物館 特任助教、博物資源学/日本史学) 概要:戦国時代の楢葉郡を領知していた猪狩家に伝わった古文書を紹介します。主家である岩城氏から発給された文書は、猪狩氏との関係性がよくわかるもので、戦国時代の在地領主のあり方を示す点で重要な史料といえます。楢葉郡内を通行した伊達政宗の礼状からは、近隣の大名同士のつながりが伺えます。文書に書かれた内容を丁寧に読むことで、戦国時代の楢葉地域の様子がどのようなものであったかを読み解いていきます。チラシ(PDF) |
 |
| 東大教室@楢葉 第5回 日程:2024年6月29日(土) 13:30〜15:00 題目:植物の教室:日本の植物分類学の父 牧野富太郎の生涯と業績 講師:池田博(東京大学総合研究博物館 准教授、植物分類学) 概要:牧野富太郎(1862−1957)は、土佐(現在の高知県)生まれの植物学者で、日本に生える全ての植物に名前をつけ、図にしようという大志を抱いて上京し、数々の困難に遭いながらもその一生を植物に捧げました。ここでは、「日本の植物分類学の父」とも呼ばれる牧野富太郎の波瀾万丈の生涯と、彼の残した業績、および近年東京大学から見いだされた牧野富太郎関係の資料について解説をしたいと思います。チラシ(PDF) |
 |
| 東大教室@楢葉 第4回 日程:2024年4月27日(土) 13:30〜15:00 題目:進化の教室:解剖学が探るからだの歴史 講師:遠藤秀紀(東京大学総合研究博物館 教授、解剖学/遺体科学) 概要:長い進化の歴史にはさまざまな出来事があったはずですが、困ったことに過去は実験室で再現することができません。そこで私は、動物の死体を解剖することで、からだの進化史に迫っています。死体には、命の過去を解明するヒントが詰まっているのです。パンダ、アリクイ、イルカ、アザラシ、カバ、そして、人知れず生きる地球のたくさんの動物たち。彼らにメスを当て、謎を解きましょう。今日の相手は、五億年の時間です。チラシ(PDF) |
 |
| 東大教室@楢葉 第3回 日程:2024年2月17日(土) 13:30〜15:00 題目:いん石の教室:星のカケラが語ること 講師:三河内岳(東京大学総合研究博物館 教授、惑星物質科学/鉱物学) 概要:いん石は、いったいどこから来て、何でできているのでしょうか? そして、それらを調べると何がわかるのでしょうか? 地球のあちこちにいん石や衝突クレーターの岩石を採りにいく話や、実際にいん石標本に触れてもらうことを交えながら、いん石が語ってくれる太陽系46億年の歴史を紹介します。合わせて、「大地とまちのタイムライン」で展示されているいん石についても、現場でくわしい解説を行う予定です。チラシ(PDF) |
 |
| 東大教室@楢葉 第2回 日程:2023年12月16日(土) 13:30〜15:00 題目:バイオミネラルの教室:貝と真珠がうみだす生体鉱物 講師:佐々木猛智(東京大学総合研究博物館 准教授、動物学) 概要:鉱物は英語ではミネラルと言います。生物がつくる硬い部分も鉱物の一種であり、日本語では生体鉱物、英語ではバイオミネラルと呼びます。バイオミネラルの代表的な例には貝殻、サンゴ、ウニの殻、脊椎動物の骨などがあり、その他にも多様な種類のバイオミネラルが知られています。生物界に見られる様々なバイオミネラルの例を紹介し、特に貝殻、真珠に関する最近の研究のトピックを紹介します。チラシ(PDF) |
 |
| 東大教室@楢葉 第1回 日程:2023年10月21日(土) 13:30〜15:00 題目:空間の教室 : 空間の創造と再生––建築と都市の歴史から学ぶ 講師:松本文夫(東京大学総合研究博物館 特任教授、建築学) 概要:空間デザインやまちづくりについて考える教室です。世界の建築や都市の歴史を通して、私たちの 住む場所がどのようにつくられてきたかを学びます。そこには創造と再生をめぐる生き生きとした人間の営みが見出せます。まずはヨーロッパを中心とする地域をとりあげます。 チラシ(PDF) |
 |